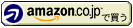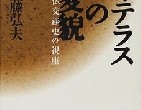花窟神社
花窟神社
当社は、社殿がなく、高さ45メートルの窟をご神体としており、熊野三山成立前の太古の自然崇拝の遺風を漂わせている。花の窟の名は、季節の花々で神をお祀りしたことに由来し、岩窟前で歌舞し、花や幡で供え飾る祭祀は、海上の道をたどる日本列島古来の祈りのかたちであったことを伝えている。

〒519-4325 三重県熊野市有馬町上地130
TEL:0597-89-4111
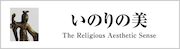
東博百選
法隆寺 夢殿 奈良時代
GO TOKYO ONLINE ロケ地
山野行楽図屏風 与謝蕪村筆
世界遺産法隆寺は、大和平野を見渡す斑鳩の宮(イカルガノミヤ)に接して、聖徳太子によって607年頃に創建。その後火災にあい、復興されたのが世界最古の木造建築群として知られる現在の西院伽藍。また斑鳩宮跡に、奈良時代に聖徳太子の菩提を祀る夢殿が建立され、夢殿を中心とした建築群が現在の東院伽藍。 円に八角の軒を出す、東院の伽藍の本堂。奈良時代に、聖徳太子の供養として、朝廷が、斑鳩宮跡に建立。堂の名前は、勝鬘(ショウマン)経、維摩(ユイマ)経、法華経のような、難解な経典の注釈、『三経義疏(サンギョウギショ)』を作成中、聖徳太子が、夢で光り輝くキンジン(金人)、救世観音(クセカンノン)に出会ったことから。


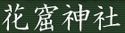



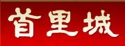


 南太平洋から東アジア全域にわたるルーツが想定されるアマテラス。古代6世紀の天武天皇のころから天皇家の祖神として考えられ、祟り神の性格が消失し、統治の神が付与される。中世神仏習合の中で“あまねくてらす”普遍的な神として変貌していく。その変貌には、日本の神仏思想の本質と矛盾が集約されていると本書は語る。
南太平洋から東アジア全域にわたるルーツが想定されるアマテラス。古代6世紀の天武天皇のころから天皇家の祖神として考えられ、祟り神の性格が消失し、統治の神が付与される。中世神仏習合の中で“あまねくてらす”普遍的な神として変貌していく。その変貌には、日本の神仏思想の本質と矛盾が集約されていると本書は語る。