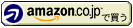-
台付からくり輪舞(リンブ)人形 茗荷屋半左衛門(ミョウガヤハンザエモン)作
江戸時代 正徳3(1713)年 東京国立博物館蔵 - 台座の棒を回すと、三味線の音に合わせて回転する、からくり輪舞人形。 繊細な細工のミニチュア、ひなを、... 続きを読む
-
菩薩半跏(ハンカ)像 法隆寺献納宝物(ケンノウホウモツ)
7世紀 東京国立博物館蔵 - 痩身で、装身具も簡素な足を組み瞑想する菩薩像。 666年朝鮮半島で百済が滅ぶ。多数の王朝の民が日本に... 続きを読む
-
蓬莱山蒔絵袈裟箱(ケサバコ)法隆寺献納宝物(ケンノウホウモツ)
平安時代 12世紀 東京国立博物館蔵 - 袈裟などの衣類を運ぶ箱。仙人が金・銀の宮殿に住むと、古代中国で言われた東の海に現れる島、蓬莱山を長寿... 続きを読む








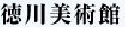

 本書紹介の室町幕府のアートディレクター同朋衆は、踊り念仏の時宗に起源する。当時、村落社会の宮座、信仰社会の念仏結社や別所、武家社会の会所で、「寄合の遊芸」が発展し、また兼好法師や鴨長明などの「評価」が貴族や武家に広がる。結果評価される幕府の月例行事を、遊芸に通じる時宗出身者が担い武家文化が育つと語る。
本書紹介の室町幕府のアートディレクター同朋衆は、踊り念仏の時宗に起源する。当時、村落社会の宮座、信仰社会の念仏結社や別所、武家社会の会所で、「寄合の遊芸」が発展し、また兼好法師や鴨長明などの「評価」が貴族や武家に広がる。結果評価される幕府の月例行事を、遊芸に通じる時宗出身者が担い武家文化が育つと語る。