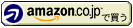-
グレ-風景 浅井忠
明治34(1901)年 東京国立博物館蔵 高野時次氏寄贈 - 佐倉藩藩士の子供で花鳥画を学び、文明開化でフランスに留学した浅井。 19世紀半~20世紀前半芸術村が... 続きを読む
-
金銅製冠帽(カンボウ)
古墳時代 5−6世紀 東京国立博物館蔵 - 透し彫りの悪霊防御のカエン(火焔)紋の内に、透し彫りの絡み合った2頭の龍。半球の飾り金具を付けた蛇行... 続きを読む
-
鼉龍(ダリュウ)鏡 団伊能氏寄贈
古墳時代 4世紀 東京国立博物館蔵 - 乳(ニュウ)は鏡の裏面(背面)のトッキ。トッキをに尾があるものは、獣の形が変形したもの。ニュウをめぐ... 続きを読む

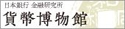










 徳川幕府第六代将軍家宣に仕えた新井白石は、進取の気性をもち元禄バブルの崩壊後の国の設計に取り組む。将軍の対外称号を「大君」から「国王」への変更、朝鮮使節の待遇改善などを処理し、金銀の海外流失や貿易の節度に関心をもち、貨幣主義と貿易不要論を貫く。本書は白石の人生の苦節と幕政改革の工夫と苦労を語る自伝。
徳川幕府第六代将軍家宣に仕えた新井白石は、進取の気性をもち元禄バブルの崩壊後の国の設計に取り組む。将軍の対外称号を「大君」から「国王」への変更、朝鮮使節の待遇改善などを処理し、金銀の海外流失や貿易の節度に関心をもち、貨幣主義と貿易不要論を貫く。本書は白石の人生の苦節と幕政改革の工夫と苦労を語る自伝。